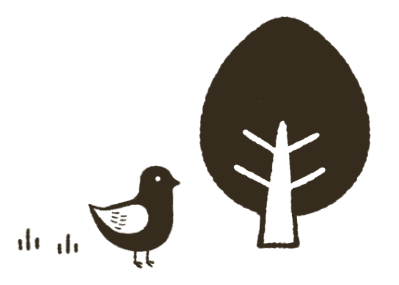中河原保育園の保育の様子を取材して頂きました。
ぜひ皆様にも御覧頂ければと思います。
●5歳児の当番活動
この保育園では「待つ保育、支える保育」を実践してきて、5歳になった子供たちがその成果をしっかり見せています。
給食の時には、5歳児がお当番活動で、全部のクラスにおしぼりなどを手分けして配ります。
みんなが出したゴミも一括にまとめて出すなどの作業も5歳児のお当番が順番に担当します。
子供たちが、人のために役に立つという気持ちを上手に深めていけることや、それぞれのクラスの人数を把握して、
その人数分のおしぼりを用意するなど、数への関心がうまれるのもねらいの一つです。
ある日、おしぼりを配るとき、1つ足りなくなったことがありました。保育士が子供たちの様子を見守っていたところ、子供たちは各クラスに配ったおしぼりの数を確かめていき、あるクラスで1個多く置いていたことに気付きました。
数が合わなかった原因を自分たちで見つけて解決しています。このような体験を重ねていくことで、
子供たちが自分の自信に変えていけけるように、保育士たちは子供たちを見守っているのです。
●保育士の専門性が生きている保育
保育士の専門性の1つとして、子供の気持ちを受け止め、寄り添うことが挙げられます。
例えば、1歳前後の時期は、歩けるようなると、少し高いところに足をかけて上りたがるなど、
大人が見て危ない行動する時があります。そのような時に、保育士は、子供の行動の背後にある気持ちを受け止め、
安全な低い台を用意して「これにどうぞ」と子供の欲求を満たす方法ができます。子供たちが何に興味があり、
どのようなことをしたいのか考えることで、あらかじめ環境を整えることができ、
子供たちの気持ちや行動を受け止められるのです。
高いところに上りたい子供の前に「どうぞ」と出したあひるを模したコの字型の台は、
保育士が牛乳パックで作ったものです。このおもちゃは色々な場面で重宝していて、
1歳を過ぎるとそこの上に登ったり、ジャンプしたりすることに使うことができます。
逆さまにすると上におままごとの道具をのせてテーブルになります。
お座りができない子供は背もたれにして、座って遊ぶことができます。いろいろな向きに変えると乗り物にもなり、
歩行が安定していない子供は歩く力がなくてもこの台にまたがって、車のように前に進むことができます。
万能なおもちゃです。
園の中にはほかにも、牛乳パックで作った道具がたくさんあります。
玄関では、靴を履き替えるときに子供が腰かける長椅子のようなものがあります。
お散歩に出かけるときにお散歩カーが準備できるまで、腰かけて子供たちが機嫌よく待っています。
保育関連雑誌には、牛乳パックで作るおもちゃなどの作り方が紹介されていて、それぞれの園では、
保育士たちが、子供の発達に見合ったおもちゃを作り、活用しています。
保育士の様々な工夫により、子供たちの育ちを支える環境が出来ているのです。